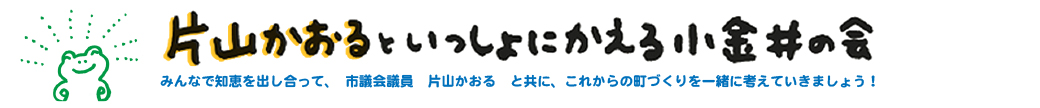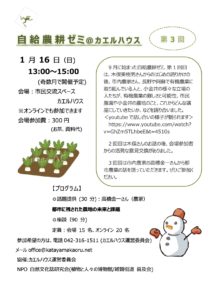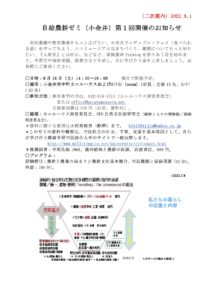日曜議会に引き続き、残時間の一般質問の通告書です。
3/1(金)13;00から13:45の予定です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーー
- 公立保育園の廃園を撤回し、子どもの権利を保障した保育行政を。今こそ子どもの権利委員会と子どもの権利条例推進計画が必要。
日曜議会に引き続き、公立保育園廃園問題と、保育行政について問う。また、2/10.11に開催された「地方自治と子ども施策」全国自治体シンポジウムや、市民団体「いかそう!子どもの権利条例の会」がまとめた記録集を受けて、「小金井市子どもの権利に関する条例」を、いかに実効性のあるものにしていくのか。
1)公立保育園段階的縮小が行われている中で、子どもの権利侵害が心配されている。子どもオンブズパーソンは独自に調査を行い、適切な措置や是正を勧告すべきではないか。また、判決を受けての対応を確認する。
2)次期のびゆくこどもプランの中で、公立保育園の役割を位置付け、認証保育所など昔から小金井の保育を支える保育所と共に、保育行政を立て直すべきである。市内を公立保育園5園を中心に5つの地域とし、民間保育園の配置、相互の交流、フォロー体制、学校との連携などを組み立て、公立保育園の定員を徐々に減らし、60人規模の園としながら、子育て支援施設や高齢者福祉施設などと複合化して、地域の子育て支援拠点機能を持つ建て替えを計画しないか。
3)子どもの権利条例と子どもオンブズパーソン条例を一体化し、より実効性のある総合条例に変えていく必要があるのではないか。子どもの権利委員会と権利条例推進計画策定について問う。
- オーガニック給食導入で、小金井の農業をより活性化しないか。
1)現在の学校給食の指針の実施状況と武蔵野市などを参考に指針の充実見直しの検討は。全国的なオーガニック給食導入の状況をどのように把握しているか。無償化の検討は。保育園での給食の状況は。
2)学校給食地場産物・有機農産物使用促進事業を活用し、学校へのオーガニック給食の導入を検討しないか。
3)農水省みどりの食料システム戦略に対する対応は。オーガニックビレッジ宣言の検討を。