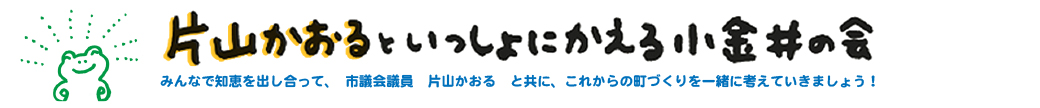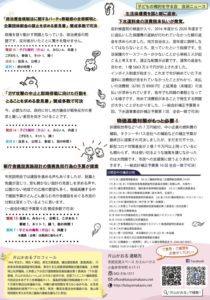5/30から6月議会(第2回定例会)が始まります。片山かおるの一般質問は6/7(金)13:00からとなりました。
1 困難女性支援新法に基づく女性支援について
厚労省のHPには『女性支援事業では、令和6年4月1日に施行された「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」(女性支援新法)に基づき、「女性の福祉」、「人権の尊重や擁護」、「男女平等」といった視点に立ち、困難な問題を抱える女性一人一人のニーズに応じて、本人の立場に寄り添って、切れ目のない包括的な支援を行います。』と掲載されている。
困難を抱えた女性、若年女性支援への市の取り組み状況を確認する。
1) 新法に対する認識は。
2) 新法に基づく計画策定はどのような状況か。都の計画と予算をどう把握しているか。
3) 一時保護委託費の状況は。保護が必要な場合の対応について。
2 共同親権と子どもオンブズパーソン
民法が改正され2年後に共同親権が導入されることになったが、子どもの権利条約に基づいた子ども主体の運用がされるのかが疑問である。子どもオンブズパーソンの役割や期待されるものに変化はあるのか。
1)共同親権導入について市民からの不安の声をどう把握しているか。市として懸念することは何か。
2)支援措置はどのような運用になるのか。
3)子どもの意見表明権はどのように保障されるのか。子どもオンブズパーソンの役割に変化はあるのか。共同親権導入している諸外国の子どもオンブズパーソンや子どもコミッショナーの役割をどう把握しているか。
4)施行前に問題点を洗い出し、自治体としての懸念や要望を国等に伝えて、制度を精査することが必要ではないか。
3 貧困ビジネスから生活保護利用者を守るために
市民団体等からの要望や交渉を続けた結果、ようやく厚労省は4/1から生活保護実施要領等を改正し、別冊問答集も改訂。これまで難しいとしてきたアパート扱いの貧困ビジネスの施設から他のアパート等への転宅が可能となった。これ以上、貧困ビジネスの施設で利用者が苦しまないように速やかに適切な対応を求める。
1)4/1に改訂された厚労省生活保護実施要領等の別冊問答集の把握と実践について。
2)生活保護制度の本来の趣旨から貧困ビジネスの施設契約や運営は外れていないか。申請の際に契約書をどのように把握しているのか。
3)居住支援相談窓口との連携は。
4)特に貧困ビジネスとの対峙の際、法的バックアップが必要。速やかに法律相談できる体制が取れないか。
5)貧困ビジネスは許さない。市民の人権を守る、という市長の意思を示さないか。